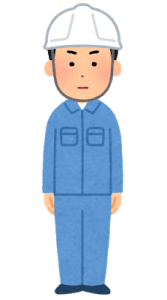倉庫ごとに倉庫管理主任者を置かなければならないことは分かったけれど、
さらに「一体、倉庫ごとに何人必要なの?」や「大きい倉庫も小さい倉庫も一律で良いの?」
など、疑問をお持ちのことと思います。
それでは、倉庫管理主任者の配置基準について、解説しますので確認してみましょう。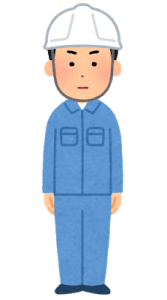
基本的には、倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければなりません。
ただし、次のいずれかの内容であれば、同一の方をその倉庫の倉庫管理主任者とすればよいこととされています。
つまり、同一の方一人の選任でよいことになります。
※次の①、②の「複数の倉庫」とは、一類倉庫と冷蔵倉庫のように、同じ種類の倉庫でなくてもよいこととされています。
| ① 同一の敷地内に設けられている倉庫、その他機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
※「その他機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫」とは、道路を挟んで両側に設置されている倉庫などで、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業などの管理業務が一体的になされていると認められる倉庫のことです。
② 同一の営業所、その他の事業所が直接管理または監督している複数の倉庫(同一都道府県内に存在するものに限る。)であって、それらの有効面積の合計値が10,000㎡以下である倉庫
※「直接管理・監督している」とは |
事業所が、倉庫の荷役や労務管理といった業務についてマニュアルを作成したり、その業務を監督するなど、それら倉庫で行われる業務についてまず責任を負う立場にある状態のことです。
そのため、ある事業者が、ある倉庫について組織上一般的な監督権限をもっている場合でも、実質的な権限をもっていない場合には、直接管理・監督していることにはなりません。
| ※有効面積の合計値の算出方法
まず、倉庫ごとに次のような係数が定められています。
一類~三類倉庫 有効面積×1.0
野積倉庫 有効面積×0.5
水面倉庫 有効面積×0.5
貯蔵槽倉庫 有効面積×0.2
冷蔵倉庫 有効面積×0.2
危険品倉庫(建屋) 有効面積×2.0
危険品倉庫(野積) 有効面積×1.0
危険品倉庫(タンク)有効面積×0.4
認定トランクルームは計算から除外
例えば、同一都道府県内にある倉庫で次のような場合で見てみましょう
一類倉庫 5,000㎡
一類倉庫兼認定トランクルーム 3,000㎡
貯蔵槽倉庫 3,000㎡
冷蔵倉庫 5,000㎡
合計すると16,000㎡で10,000㎡を超えてしまいますが、先ほど挙げました係数をかけてみると次のようになります。
一類倉庫 5,000㎡×1.0=5,000㎡
一類倉庫兼認定トランクルーム 3,000㎡×0=0㎡
貯蔵槽倉庫 3,000㎡×0.2=600㎡
冷蔵倉庫 5,000㎡×0.2=1,000㎡
このようになり、有効面積の合計値は6,600㎡で10,000㎡を下回り、この場合、倉庫管理主任者は一人でよいこととなります。 |
同一敷地内の場合や、有効面積の合計値が10,000㎡以下で倉庫面積が大きくなく、他の都道府県にまたがるような場合などでなければ、倉庫管理主任者は一人選任すればよいこととなります。